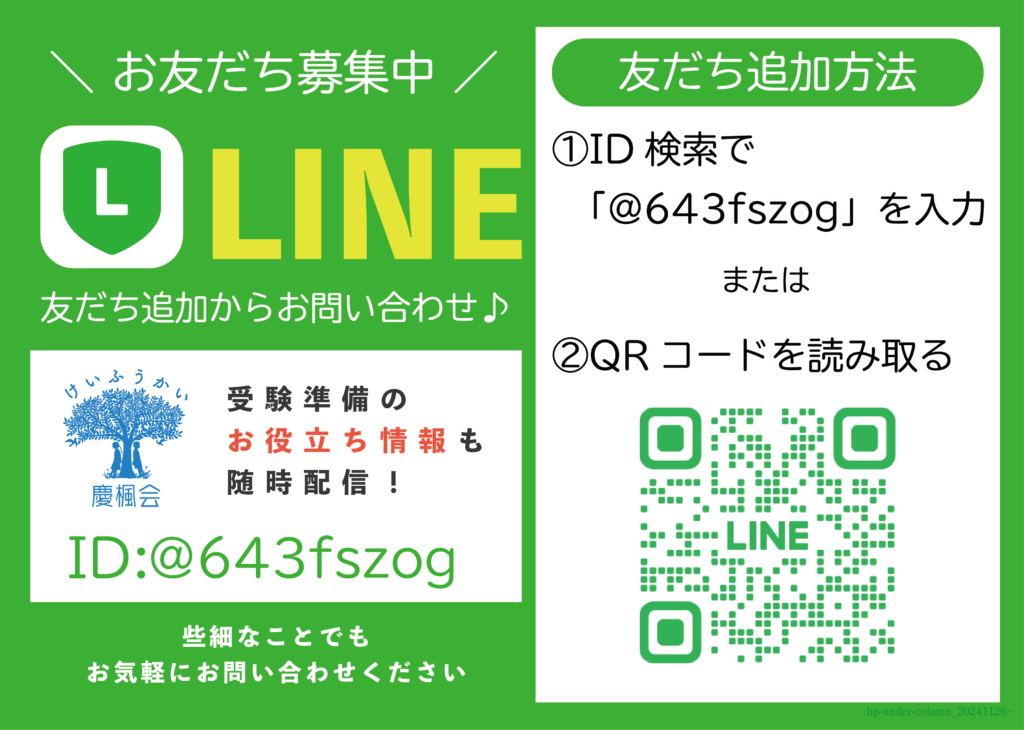【コラム】東洋英和女学院小学部に受かる子
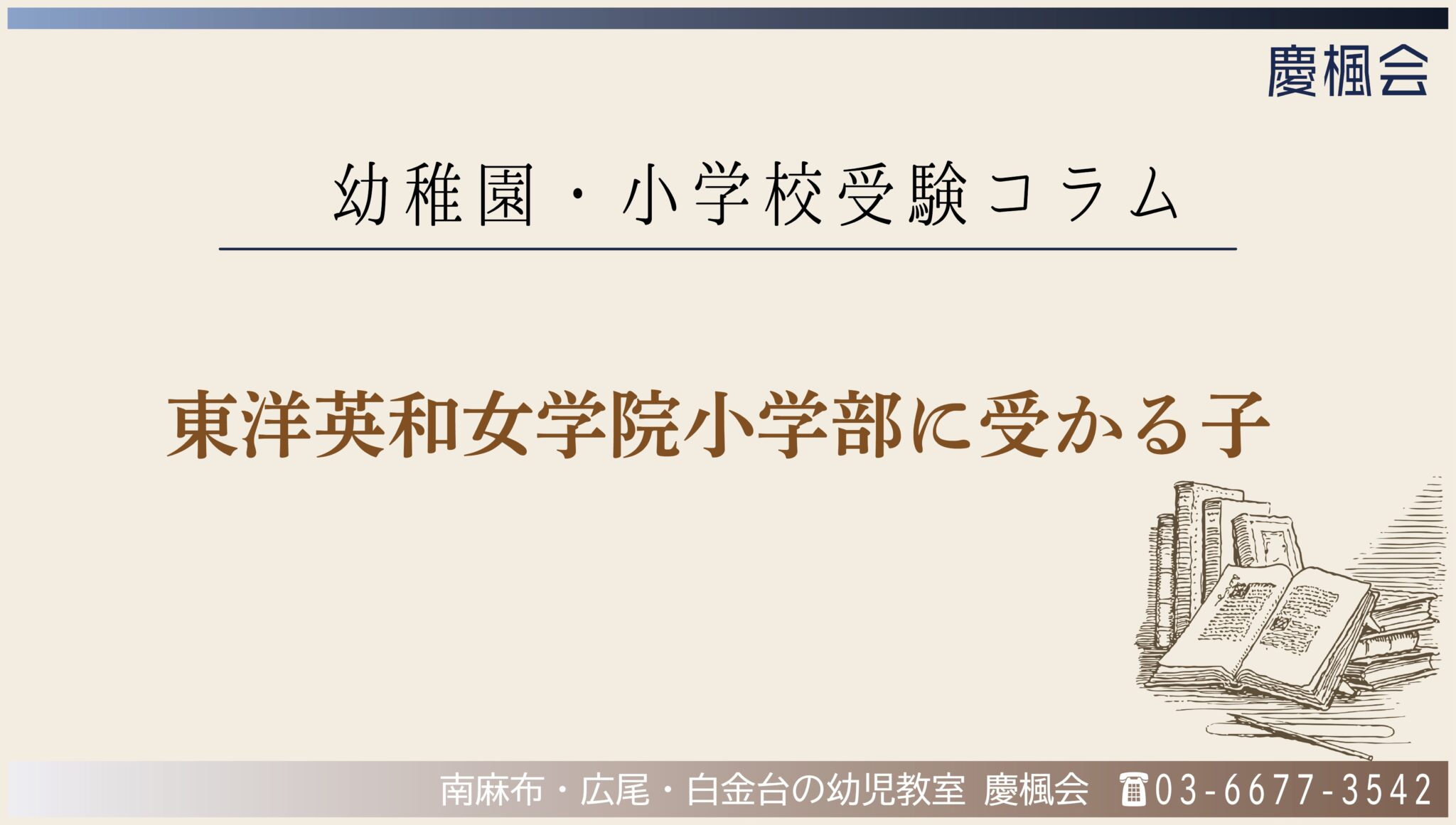
こんにちは、小学校受験コース主任の松下健太です。
さわやかな春の光に新緑が照らされるこの季節、年長になったお子さまとの新しい日常が少しずつ形作られてきた頃かと思います。新しいクラスやお友達との生活にも慣れ、すくすくと成長していく姿に、保護者の皆さまも喜びを感じていらっしゃることでしょう。
受験に向けての準備がいよいよ本格化するこの時期、慶楓会にもたくさんのご相談が寄せられています。中でも特に高い関心を寄せられる学校の一つが東洋英和女学院小学部です。その明るい校風と、神さまと人に心から仕える女性を育てる女子教育に惹かれる方が、多くいらっしゃいます。
1884年の創設以来、キリスト教の教えに根ざした女子教育を一貫して貫いてきた東洋英和女学院。その長い歴史の中で大切にされてきたのは、単に学力の向上を目指すということにとどまらない、人としての在り方、生き方そのものです。聖句に基づく「敬神奉仕」という言葉に込められた思いが教育の根幹に据えられています。
このような伝統ある学校においては、入学考査においても「何かができる」とか「何かを知っている」といった、表面的な技能や知識によって選抜が行われるわけではありません。
今回は、もともと私立小学校の現場で、実際の入学考査に携わっていた経験を踏まえながら、実際に合格されたご家庭に共通するお子さまの姿やご家庭のあり方を、それぞれ3つの視点からまとめてご紹介いたします。これから受験をお考えのご家庭の皆さまにとって、日々の家庭教育や子育てを見つめ直す一つの指針となれば幸いです。
子どもの特徴
1. 礼儀正しい所作や言葉遣いが、自然なかたちで身についている
東洋英和が大切にしているのは、見た目の華やかさではなく、内面からにじみ出る品位です。在校生には、挨拶の声、ものの受け渡し、座り方や歩き方など、どの動きにも丁寧さがあります。そしてそれらが「見せるため」ではなく、他者を思う姿が日常に根付いた自然体であることが伝わってきます。
例えば、教室に入るときのドアの開け方一つとっても、「バタン」と勢いよく開けるのではなく、静かに開けて、後から来る人のためにもドアを支え、閉める際にも音を立てないよう配慮する姿が見られます。また、先生や友達の話を聞くときには、相手の目を見て、うなずきながら耳を傾け、質問をされたら「はい」と返事をしてから答えるといった、基本的な対話の姿勢も身についています。
これらは、ご家庭での何気ない日々のやりとりの中にある繰り返しの積み重ねの賜物です。「ちゃんとしなさい」と叱るのではなく、親御さま自身が手本となり、言葉や動作を整えていく中で、礼儀が”生き方”として身についてきます。
実際の入学考査では、試験官が特別に「礼儀正しくしなさい」と指示して、その様子が見られるということはありません。しかし、お子さまが特別の指示を受けなくとも、自然と示す所作や受け答えの中に、日々の育ちがにじみ出ています。それは一朝一夕に身につくものではなく、家庭での毎日の心がけが生んだ自然な姿勢なのです。そうした「作り上げたものではない真の品位」が評価されるのが、東洋英和の考査だと言えるでしょう。
2. 「自分がどう見られるか」よりも、「今、誰のために何ができるか」を考えている
多くの学校が「自己主張」や「積極性」を重んじる一方で、東洋英和が大切にして育もうとする資質は、他者へのまなざしです。英和生はみな、困っているお友達にそっと手を差し伸べたり、自分の意見を言う前に周囲の様子を見たりと、誰かの役に立ちたい、みんなで良い時間を過ごしたいという思いが自然な行動として表れています。
慶楓会に以前に通われていたお子さまの例をご紹介します。入塾当初は、慶楓会に通う前に習っていたどこかの幼児教室で聞いてきたのか、相談の場面になるとすぐに「じゃあ○○にしない?」と周囲の意見も聞かずに自分の意見を真っ先に主張して、その場の主導権を握ろうとするような姿がありました。そこで、「自分の考えを真っ先に伝えるのではなく、まずは他の人の意見を聞くことが大切なんだよ」ということを、根気強く指導し、具体的な相談場面を繰り返し設定して、対話の練習を重ねました。するとしだいに、その子は自分の意見をすぐに発表しようとするのではなく、まずは周りの子が話しやすいように場の雰囲気をつくることができるように、変化していきました。「〇〇ちゃんはどう思う?」と静かな子に話す機会を作ったり、友達が発言したときには「なるほど」と反応したりする姿を示すことができるようになり、試験にも見事に合格されました。
また別の合格されたお子さまは、製作活動の際に、自分の作品を早く仕上げることより、困っている友達に「これ、使う?」と材料を分けてあげたり、「ここはこうするといいよ」と教えてあげたりすることを自然としていました。このような姿勢は、東洋英和で大切にされる「他者への奉仕」という価値観に合致するものです。
「私は○○がしたい」という自己表現よりも、「みんなで楽しくできるにはどうしたらいいかな?」と考える。そのような身近な周囲のお友達への姿勢が、”他者に仕える心”としてやがて昇華され、無理なく自然な振る舞いとしてにじみ出ていく、それが英和が求めるお子さまの姿なのです。
こうした資質は本来、ご家庭での兄弟姉妹や祖父母との関わり、地域や教会などのコミュニティでの経験を通して育まれていくものであり、幼児教室で「こういう場面ではこう言いなさい」と指示されて育つものではありません。
3. 小さなことにも感謝し、喜びをもって毎日を生きている
「今日もお弁当おいしかったよ、ありがとう」 「先生が褒めてくれて、うれしかった」 「お庭のお花が咲いていて、きれいだったよ」
そんなふうに、日々の小さな出来事に心を動かし、感謝を素直に言葉にできるのが、合格したお子さまたちの共通点です。
東洋英和の入学考査における面接では、「夏休みに楽しかったことは何ですか?」「お家でどんなお手伝いをしていますか?」といった質問がよくなされます。このような問いかけに対して、合格されたお子さまたちは、控えめに見える出来事でも、心から喜び、感謝している様子が伝わる答え方をしています。それは単に「楽しかったです」という言葉だけでなく、表情や声のトーンからも伝わってくる本物の喜びなのです。
ある合格されたお子さまは、「夏休みに楽しかったことは何ですか?」という質問に対して、「海に行く日、最初は雨で残念だなと思っていたら、知らないうちに雨が上がって虹が出ていました。神様がきれいな虹を見せてくれたんだなと思いました」と答えたそうです。また別のお子さまは、「お家でのお手伝い」を聞かれて、「お母さんが疲れているときに、肩をトントンしてあげるのが好きです。ありがとうって言ってもらえるのが嬉しいからです」と答えていました。
目の前にある苦難や困難の負の面に支配されるのではなく、与えられた命を喜び、日常の恵みに気づくこと。これはまさに、東洋英和が育もうとしている「神さまに生かされる人間」としての姿勢です。無理に覚えた”きれいごと”ではなく、心の奥底から自然と湧き上がる感謝や喜び。それが、キリスト教的価値観を育もうとする先生方の心に、確かに届くのです。
このような姿勢は、ご家庭での日々の会話や、感謝の気持ちを伝え合う習慣、自然や季節の移り変わりに目を向ける時間の中で、少しずつ育まれていくものです。
家庭の特徴
1. キリスト教の価値観や東洋英和の教育方針への深い理解がある
東洋英和の教育は、神さまをすべての判断の中心におく姿勢に根差しています。合格されたご家庭は、必ずしも全てがクリスチャンというわけではありませんが、「信仰があるかどうか」という形式にかかわらず、その価値観に真摯に向き合い、家庭生活の中にも祈りや感謝の心が自然と息づいていることが感じられます。
例えば、食事の前に形式的に「いただきます」と言うだけではない深い感謝の念を持つことが大切です。命をいただくということそれ自体だけでなく、食材を育ててくださった方々や運んでくださった方々、調理してくださった方々と、自らの口に運ぶまでの間にたくさんの人の手を通ってきたこと、その全てを神さまが守ってくださったことへの感謝の気持ちを込める。日々の生活の中で起きる出来事を「偶然」で済ませず、「誰かの見えない支えがあったから」と受け止める。自分たちの幸せだけでなく、世界で苦しんでいる人々のことも心に留めて祈る。そういった姿勢が、特別なことではなく日常として定着しているご家庭が多いのです。
願書や面接でも、その理解が表層的な説明にとどまらず、「日々の暮らしの中でどのように生かされているか」が具体的に語られていることが印象的です。「キリスト教に基づく教育を求めています。優しい子になってほしいです」という言葉だけでなく、実際にどのような価値観を、子育ての中で大切にしているかという実体験が伴っていることが大切です。
ある合格されたご家庭では、面接で「どのような子に育ってほしいですか」という質問に対して、「自分の命も、隣人の命も、いずれも等しく神さまから与えられた大切なものだと知り、自らも大切にし、また他者を思いやれる子になってほしい」とお答えになったとのことでした。
東洋英和の教育方針を理解するということは、「評判の良い学校だから」ということではなく、その根底にあるキリスト教的価値観、すなわち「神を敬い、人に仕える」という姿勢を理解し、家庭生活の中にも取り入れようとする意識があることを意味します。
2. 謙虚で誠実、「末席に座らせていただく」心を忘れない
東洋英和の受験では、親御さまの学歴や経歴よりも、ご家庭の人柄や姿勢そのものが問われます。合格されたご家庭に共通するのは、「私たちはまだまだ学ばせていただく立場です」という謙虚な姿勢です。面接の場でも、話す内容だけでなく、佇まいや言葉の端々に誠実さと慎み深さが自然と表れているのです。
例えば、東洋英和の面接では、保護者の方に「お子さまの長所と短所」を尋ねることがあります。このとき、お子さまの長所を語る際にも、「私たちがこのように教えた結果、○○ができるようになりました!」と鼻息荒く答える方は信じられないことに一定数いらっしゃいます。しかし合格されたご家庭の多くは、「生まれながらに神さまから与えていただいた感性を大切にし、励ましながら見守ってまいりました結果…」と謙虚な姿勢を崩さず、短所については「まだまだ親としての関わり方が足りていないところがあり…」と自らの課題として捉える傾向があります。
また別の質問例として、「なぜ東洋英和を志望されたのですか」というものがあります。この問いに対して、「その理由は3つあり、1点目は……!」という上から目線のプレゼンを披露するのではなく、「私たち親自身も御校の教育を通して成長させていただきたいと思っています」といった、学校と共に歩みたいという謙虚な姿勢を示されるご家庭が求められているのです。
慶楓会での受験対策の中でも、「どう答えるか」という形式的な指導ではなく、ご家庭の本質的な価値観や姿勢がにじみ出るような関わり方を重視しています。なぜなら、表面的な受け答えはすぐに見抜かれてしまうからです。
特に留意すべきは、こうした姿勢が「面接のためだけに用意されたアピール」ではなく、日常の中で実践されている生き方であることが望まれているということです。願書の記述や面接での受け答えから、普段の生活における謙虚さや誠実さが自然と伝わってくるのです。願書に何を書くかと考える前に、まずは自らの生き方を見つめ直す。それが、学校と家庭の信頼関係を構築する基盤となります。
3. 奉仕の心を持ち、学校との信頼関係を大切にしている
東洋英和では、学校とご家庭が共に子どもを育てるパートナーであることが前提となっています。合格されたご家庭は、「学校に何をしてもらえるか」ではなく、「私たちは何を貢献できるか」という視点を持ち、入学後の行事や奉仕活動にも喜んで関わる心構えをお持ちです。
東洋英和の面接では、「入学後にどのような形で学校に関わろうと思っていますか」という趣旨の質問項目があります。この問いに対して、合格されたご家庭の多くは、具体的な奉仕の姿勢を示されています。例えば、「母の会や父の会の活動、学校行事に積極的に参加し、できる限りの貢献をしたい」「自分の職業や経験を生かして子どもたちの教育に役立てることがあれば、いつでも協力したい」「聖書の会や教会活動にも参加し、学校の精神を家庭でも実践していきたい」といった内容です。
ここで大切なのは、「できること」を具体的に示すことのみならず、「まずは学校の方針を謙虚に学び、その上で自分にできることを見つけていきたい」という柔軟で誠実な姿勢です。
「自分たちにできることは微力かもしれないが、子どもたちが神さまの愛の中で育つ環境づくりのために、学校のご方針に従いつつ、我が身にできることは全て喜んで行わせていただくことで、共に歩ませていただきたい」といった真摯な姿勢が、何よりも求められています。ある熱心なご家庭は、「これまで教会の活動やボランティアを通じて奉仕の精神を学ぶ機会をいただいてまいりました。御校でも、これまでの学びを活かす場が与えられましたら幸いです」と、ご自身の経験に基づいた思いを伝えられていました。
このような姿勢は、学校との対話において必ずにじみ出てくるものです。学校との深い信頼関係のもとに、誠意と行動で謙虚に仕えようとする姿が、東洋英和にふさわしいご家庭として受け入れられているのだと感じます。
入学考査で見られる具体的なポイント
東洋英和女学院小学部の入学考査では、ペーパーテストだけでなく、行動観察や面接を通じて、お子さまとご家庭の姿勢や価値観が多角的に評価されます。ここでは、考査の各場面で特に注目されるポイントについてお伝えします。
お子さまの考査で見られるポイント
ペーパー・知育テストの場面
単に問題が解けるかどうかだけでなく、指示を正確に聞いて理解する力、落ち着いて考える姿勢、わからないときの対応の仕方などが見られます。「できた・できない」という結果だけでなく、その過程や取り組む姿勢が重視されます。
行動観察の場面
集団での活動や製作など、様々な場面での振る舞いが観察されます。特に、順番を守る、友達と協力する、先生の話をしっかり聞く、困っている友達に手を貸すなど、他者との関わり方が重視されます。また、自分の思い通りにならなかったときの対応や、予想外の状況での対応力も見られるポイントです。
面接の場面
お子さまとの面接では、質問に対する答え方だけでなく、目を見て話せるか、はきはきと応答できるか、自分の言葉で素直に表現できるかなどが評価されます。また、「好きな遊びは何ですか」「お家でのお手伝いは何をしていますか」といった質問を通して、日常生活の様子や家庭での関わりも垣間見ることができます。
保護者面接で見られるポイント
保護者の方との面接では、以下のような点が特に重視されます:
- 東洋英和を志望する理由
キリスト教教育・女子教育への理解と謙虚な姿勢があるか - 子育ての方針
「神を敬い、人に仕える」という東洋英和の理念に沿った子育てをしているか、また今後もそのような方向性で子育てをしていく意志があるか - 家庭の宗教観
必ずしもクリスチャンである必要はありませんが、キリスト教の価値観に対する理解と尊重の姿勢があるか - 学校への協力姿勢
学校と家庭が共に子どもを育てるという意識があるか、学校行事や母の会・父の会の活動などへの前向きな姿勢があるか
面接官は、言葉だけでなく、保護者の方の表情や態度、言葉の選び方などから、ご家庭の真の姿勢を読み取ろうとしています。大切なのは「良く見せよう」とすることではなく、誠実に、そして謙虚に自分たちの思いを伝えることです。
ちょっとした言葉遣いに、普段の考え方が現れてしまうものです。
東洋英和に向けた家庭での準備
ここまで東洋英和女学院小学部に合格されたお子さまとご家庭の特徴についてお伝えしてきましたが、「では具体的に家庭でどのような準備をすればよいのか」というご質問も多く寄せられます。以下、いくつかのポイントをご紹介します。
日常生活の中での心がけ
1. 感謝と祈りのある生活
食事の前後の感謝の言葉、就寝前の一日の振り返りと祈り、日々の出来事に対する感謝の気持ちを表現する習慣など、小さなことからでも取り入れてみてください。「当たり前」に思えることへの感謝の気持ちを家族で分かち合う時間は、とても大切です。
2. 礼儀作法の自然な習得
「〇〇しなさい」と命令するのではなく、親自身が手本となって、挨拶、言葉遣い、食事のマナー、人との接し方などを示していくことが効果的です。家族との会話の中で「ありがとう」「ごめんなさい」「お願いします」などの言葉が自然に交わされる環境づくりを心がけましょう。
3. 奉仕の心を育む機会
家庭内でのお手伝い、地域の清掃活動、教会や地域のボランティア活動など、「誰かのために何かをする」経験を意識的に取り入れることで、奉仕の心が育まれます。その際、「させられている」という感覚ではなく、「誰かの役に立てて嬉しい」という喜びを感じられるような関わり方が大切です。
教育的な関わり
1. 聖書や童話を通した価値観の共有
キリスト教の絵本や童話、または宗教的な価値観を含む教えのある絵本の読み聞かせを通して、愛や思いやり、赦しといった価値観に触れる機会を作りましょう。難しい教義を理解させる必要はなく、物語を通して心に響く体験を重ねることが大切です。
2. 自然や芸術との触れ合い
神さまが創造した自然の美しさに触れる機会や、音楽、美術などの芸術に親しむ時間を持つことで、感性や感謝の心が育まれます。季節の移り変わりや小さな生き物の観察、家族での音楽鑑賞や美術館訪問など、心を豊かにする体験を大切にしましょう。
3. 他者との関わりの場づくり
同年代の子どもたちとの遊びの機会はもちろん、年齢の異なる子どもたちや高齢者など、様々な人との交流の場を意識的に設けることで、相手に合わせた振る舞いや思いやりの心が育ちます。教会の日曜学校や地域の子ども会などの活動も有効です。
「受かる子」をつくるのではなく、共に育っていく歩みを
「受かる子」に近づけようとするあまり、つい型にはめてしまったり、無理に「よく見せよう」としてしまったりすることもあるかもしれません。しかし、本当に大切なのは、その子がその子らしく育つことを信じ、丁寧に寄り添い続けることです。
東洋英和の入学考査は、「試験のための特別な準備」で乗り切れるものではありません。むしろ、日々の生活や関わりの中で自然と身についてきた姿勢や価値観が問われるものです。だからこそ、受験直前になって慌てて対策するのではなく、普段からの積み重ねが大切なのです。
“敬虔に、丁寧に、誠実に”。 それは東洋英和が願う子どもの姿であり、同時にご家庭にも求められる姿勢です。そして、そうした日々の歩みを大切にしているご家庭にこそ、やがて受験という一つの節目が、あたたかな実りとなって返ってくるのだと思います。
もし、その歩みの中で迷いが生まれたときには、どうぞ慶楓会を頼っていただければと思います。キリスト教の価値観や東洋英和への深い理解を持つ講師が、ご家庭と同じ目線でお話を伺い、共に考えさせていただきます。表面的な「受験対策」ではなく、お子さまとご家庭にとって真に価値ある教育の道筋を、ともに探っていくことができればと願っています。
心からの祈りをもって、お子さまとご家庭の歩みを応援しております。
執筆
慶楓会 小学校受験コース 主任 松下健太
慶楓会では、元私立小学校教員を筆頭とする優秀な講師陣が、私学の文化を熟知した上で、表面的な取り繕いではなく本質的な力を育てることにより受験に臨んでいきます。非常に高い水準の知見が集積されており、その知見をご家庭と全て共有することで、保護者の皆様は、正しい道筋に沿って安心して受験対策を進めていくことができます。
非常に高い専門性を備えた指導者のいる少人数教室「慶楓会」に、一度足を運んでいただければと思います。
お問い合わせは、公式LINEのご登録より、お気軽に行っていただけます。
体験授業・ご面談も随時承ります