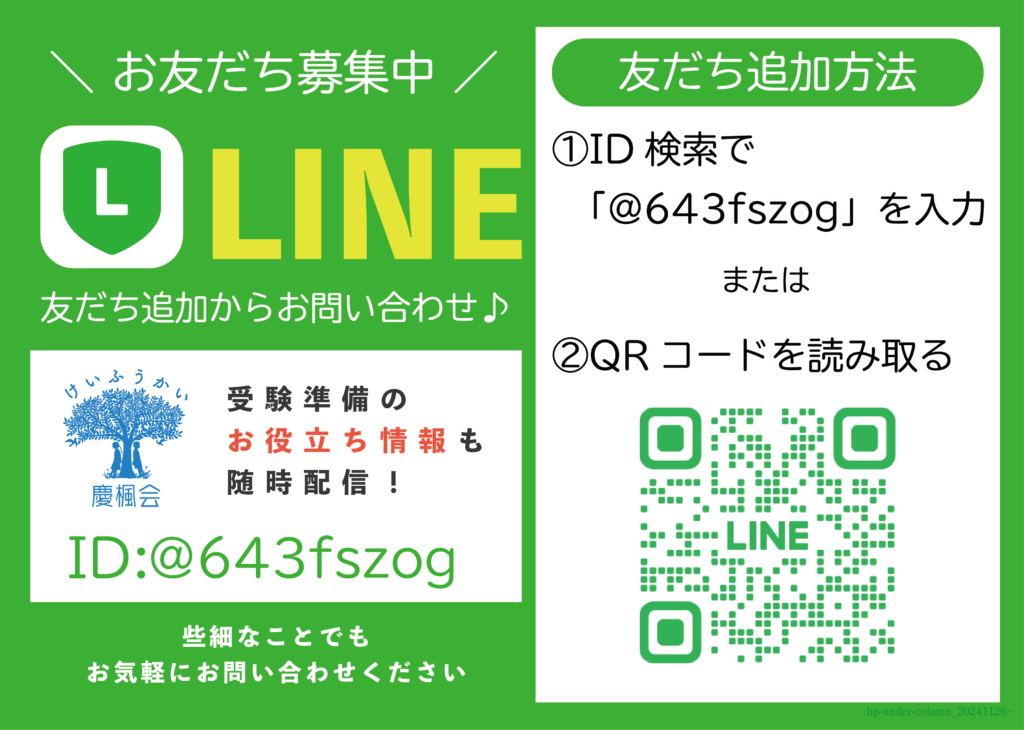【コラム】考査まで残り2ヶ月の過ごし方(2025最新版)
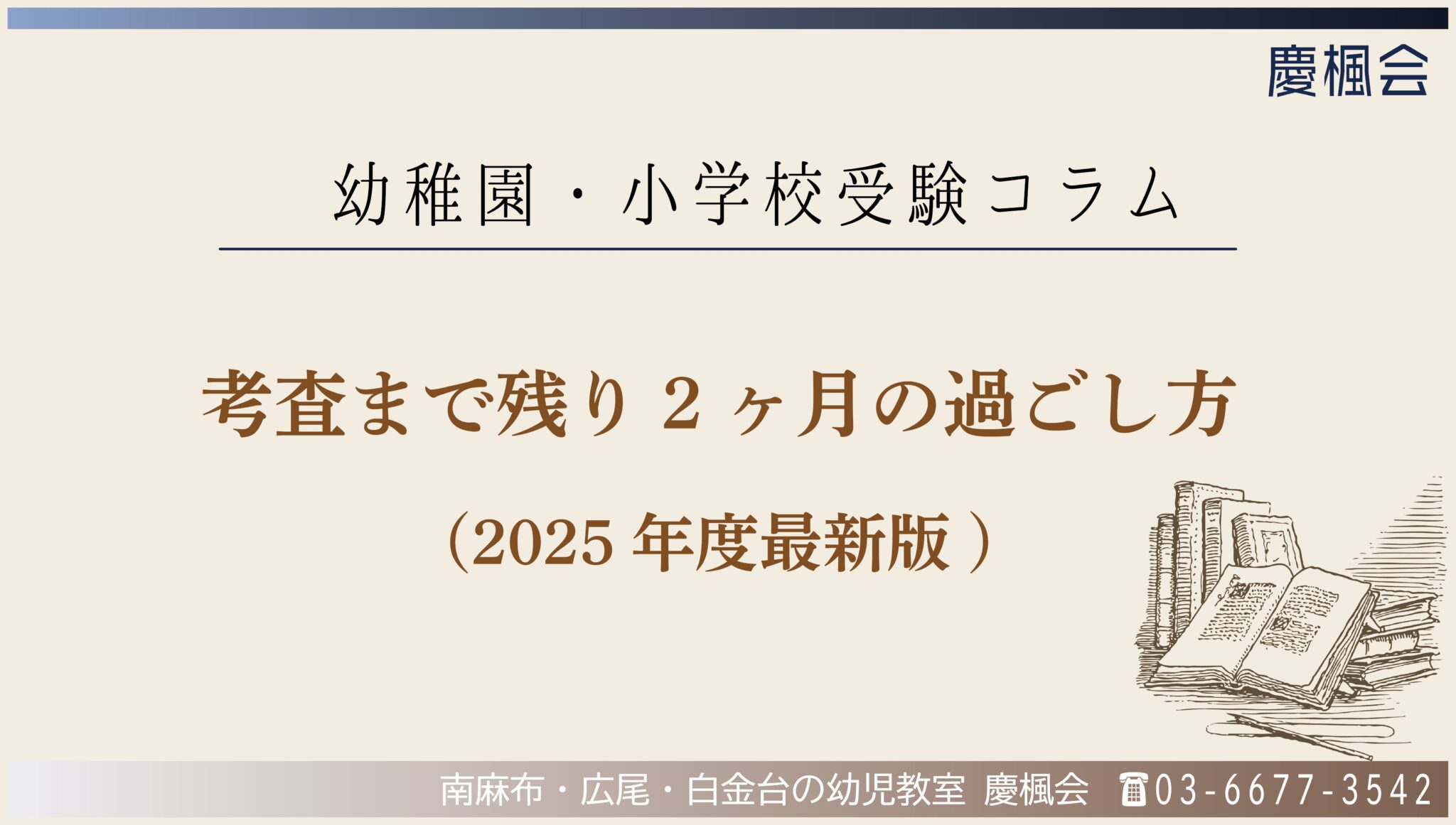
皆さん、こんにちは。慶楓会小学校受験コース主任の松下健太です。
少しずつ、朝夕に涼しい風を感じるようになり、夜には虫の声が響く季節となりました。受験を控えるご家庭では、いよいよ本格的な直前期を迎え、お子様と共に歩んできた準備の日々を振り返りながら、最後の仕上げに向けて気持ちを新たにされていることと思います。
この残り2ヶ月という貴重な時間は、これまで積み重ねてきた力を確実に発揮できる状態に整える重要な時期です。2025年度入試の最新傾向を踏まえながら、学習面・制作面・行動観察・生活習慣の各側面において、具体的で実践的な準備のポイントをお伝えいたします。
学習編:確実性を重視した基礎力の完成
直前期における学習の核心は「基礎と標準レベルの問題を、時間内に確実に正解する力」の完成にあります。新しい単元や難易度の高い問題に挑戦するよりも、既に学んだ内容の定着度を高めることに集中しましょう。
毎日の学習では、時間を測って問題に取り組む習慣を徹底してください。間違えた問題については、翌日必ず解き直しを行い、なぜ間違えたのかを親子で確認することが大切です。特に苦手分野が明確になっている場合は、その部分に重点を置いた復習時間を設けることで、弱点を着実に補強できます。
2025年度の出題傾向として注目すべきは、知識の暗記のみで対応できる単純な出題ではなく、「思考の筋道を問う問題」の増加です。答えに至るまでの過程を論理的に説明できることが求められる場面が多くなっています。日常会話の中で「どうしてそう考えたの?」「他にも方法はあるかな?」といった問いかけを心がけ、お子様が自分の思考を言葉にする練習を重ねてください。
また、条件を整理して順序立てて考える力も重要視されています。複数の情報を組み合わせて答えを導く問題では、まず条件を整理した上で、一つずつ確認しながら進める習慣を身につけることが効果的です。
制作編:発想力と表現力を育む絵画・工作指導
絵画や工作の課題では、技術的な巧みさ以上に「独創的な発想」と「それを言葉で表現する力」が評価の中心となります。作品制作の後には必ず振り返りの時間を設け、お子様が自分の作品について語る機会を作ってください。
具体的には、なぜその色や形を選んだのか、制作中にどのような工夫をしたのか、完成した時の気持ちはどうだったかを、お子様自身の言葉で説明させるようにしましょう。親御様は「ここの部分はどんな気持ちで描いたの?」「この色を使った理由は何かな?」といった問いかけを通じて、お子様の思考を引き出す役割に徹することが重要です。
制作過程で困ったことや失敗したことがあれば、それをどのように乗り越えたかも大切です。
また、考査当日の発表場面では、自分自身の体験に基づいた具体的で生き生きとした説明が高く評価されます。
近年の傾向として、従来の個人制作に加えて、複数の子どもが協力して一つの作品を作る課題も出題されています。家庭でも兄弟や友人と共同制作を体験し、役割分担や意見調整の経験を積んでおくと良いでしょう。
行動観察編:協働性と自主性の調和
行動観察課題において2025年度に特に注目されているのは「仲間と遊びを発展させる力」です。慶應義塾系の学校では従来から重視されてきた観点ですが、今年度はより具体的で多様な場面設定で評価されることが予想されます。
単に積極的に参加するだけでなく、周囲の友達の様子を観察し、みんなが楽しめるような提案ができることが求められています。遊びの輪に入れずにいる友達に自然に声をかける、ルールが分からない友達に優しく教える、といった思いやりのある行動が重要です。
ここ数年の各校の出題傾向を見ると、従来の自由遊び形式に加えて、協働課題や集団討論形式の問題が増加しています。複数の子どもが一つの目標に向かって協力する場面で、各自がどのような役割を果たし、どのようにコミュニケーションを図るかが詳細に観察されています。
日常生活では、順番を守って待つこと、指示を最後まで聞いてから行動すること、困っている人に気づいて手助けすることを意識して過ごしましょう。これらは家庭での兄弟との関わりや、公園での遊び、習い事での集団活動を通じて自然に身につけることができます。
また、即座に状況を理解し、適切な言葉で自分の考えを伝える「瞬発的な言語化力」も重視されています。日頃から「今どんな気持ちだった?」「どうしたらもっと楽しくなるかな?」といった質問を通じて、感情や思考を言葉にする練習を積み重ねてください。
生活・心構え編:心身の安定が生む自信
健康管理の徹底
季節の変わり目である直前期は、体調管理が学習面での準備と同じかそれ以上に重要な意味を持ちます。規則正しい生活リズムの維持を最優先とし、特に起床時間と就寝時間を一定に保つよう心がけてください。
朝食は一日の活動エネルギーの源となるため、栄養バランスを考慮した内容を安定して摂取できるよう準備しましょう。考査当日も普段と同じメニューで安心して臨めるよう、今から朝食の内容を整えておくことをお勧めします。
感染症対策として、手洗いとうがいの習慣は継続的に実践し、人混みを避ける配慮も必要です。軽い運動や外遊びを通じて体力を維持し、免疫力を高めることも大切な準備の一つです。
睡眠の質にも注意を払い、就寝前のテレビやタブレット使用を控えめにし、リラックスした状態で眠りにつけるよう環境を整えてください。
精神的な安定と情報との向き合い方
親御様の心の状態は、お子様の精神的安定に直接影響します。SNSで流れる受験情報や保護者同士の会話で得る様々な噂に一喜一憂することなく、「今日できることに集中する」という姿勢を保つことが何より重要です。
不確かな情報に振り回されそうになった時は、信頼できる情報源(学校説明会や塾からの正式な連絡など)で事実確認を行い、冷静な判断を心がけましょう。お子様の前では常に落ち着いた態度を保ち、「大丈夫、あなたなら必ずできる」という安心感を伝え続けてください。
日常生活に根ざした実践的準備
考査で求められる基本的な生活態度は、特別な訓練ではなく日常の習慣から自然に身につくものです。朝の身支度を一人で最後まで完成させる、靴を揃えて脱ぐ、使った物を元の場所に戻す、といった基本動作を毎日確実に実行することが大切です。
列に並んで待つこと、静かに人の話を聞くこと、返事をはっきりとすることも、普段の生活の中で意識的に練習できます。これらの行動は考査当日の態度評価に直結するため、今から習慣として定着させることが効果的です。
本番シミュレーションの活用
直前期には、考査当日の流れを想定した模擬体験を家庭で実施することをお勧めします。起床時間から会場到着、待機時間、課題実施まで、一日の流れを実際に体験してみることで、お子様の不安を軽減し、当日の行動をスムーズにできます。
初めての環境や初対面の大人との関わりに慣れるため、普段とは異なる場所での学習や、知らない大人からの質問に答える練習も有効です。ただし、過度な負荷をかけることは避け、お子様の様子を見ながら適度な範囲で実施してください。
親子の絆を深める時間:穏やかな信頼関係が生む最大の力
この2ヶ月間は、学習や練習の時間と同じくらい「心穏やかに過ごす親子の時間」を大切にしてください。一緒に散歩をする、好きな遊びを楽しむ、ゆっくりと食事を摂るといった何気ない日常の積み重ねが、お子様の心の安定と自信の源泉となります。
お子様が不安になったり、思うようにいかずに落ち込んだりした時には、結果よりもその時々の努力や成長を認める言葉をかけてあげてください。「今日も頑張ったね」「この前よりもできることが増えたね」といった声かけが、お子様の自己肯定感を支えます。
親御様が「あなたを信じている」「どんな結果でもあなたは大切な存在」という気持ちを言葉と態度で示すことが、お子様にとって何よりも大きな力となります。この信頼関係こそが、考査当日にお子様が自分らしさを発揮するための土台となるのです。
直前期を成長の糧として
残された2ヶ月という時間は、時には焦燥感をもたらすかもしれません。しかし、この期間を「最後の追い込み」ではなく「これまでの学びを確実なものにする仕上げの時間」として捉え直すことで、親子共に前向きな気持ちで過ごすことができます。
毎日の小さな積み重ねが確実な自信につながり、生活リズムを整えることで心身の安定が生まれ、親子で支え合うことで最後まで歩み抜く力が育まれます。こうした日々の生活や、準備の過程そのものからこそ、本来、幼児は物事の道理を学んでいくものです。
日常の当たり前を大切にした生活の中から学び、人として大きく成長していく道のりを応援する気持ちを持ち続けるようにしましょう。
受験の結果がどうであれ、この期間に親子で共有した時間と体験は、お子様の人生において貴重な財産となります。目標に向かって努力し続けた経験、困難を乗り越えた体験、家族で支え合った記憶は、これから先の人生でお子様を支える力となるはずです。
残り2ヶ月を、焦りではなく希望を胸に、お子様の成長を信じて力強く歩んでいきましょう。親御様とお子様の深い信頼関係が、必ずや最良の結果へと導いてくれることを確信しています。
執筆
慶楓会 小学校受験コース 主任 松下健太
お問い合わせは、公式LINEのご登録より、お気軽に行っていただけます。
体験授業・ご面談も随時承ります