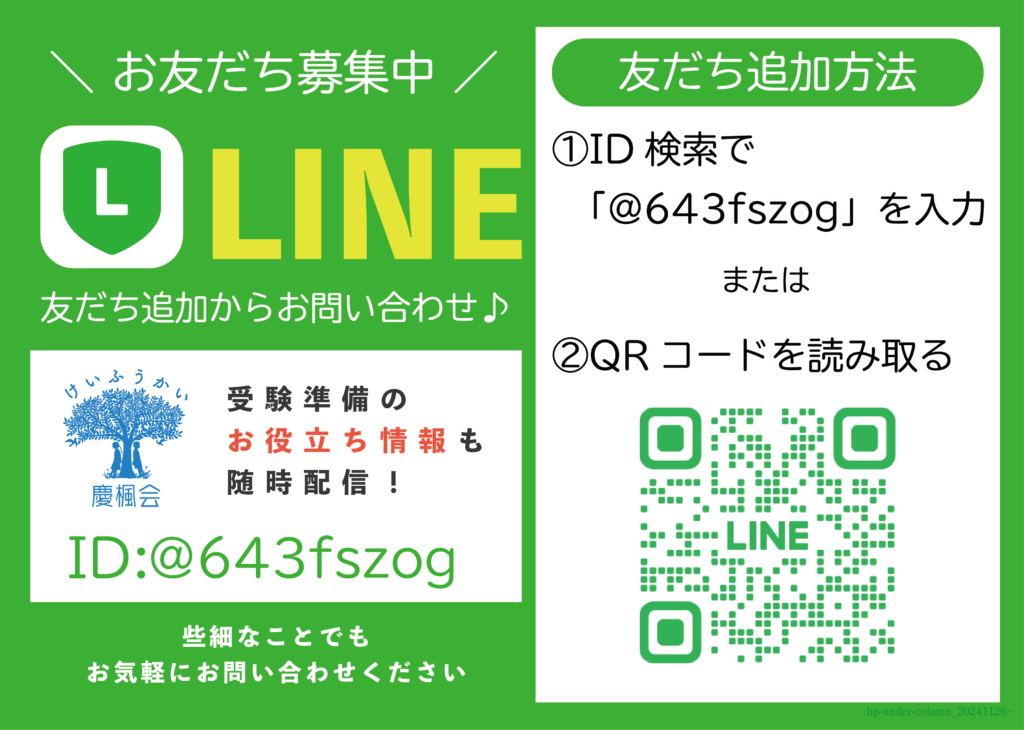【コラム】成功する人は、もう始めている
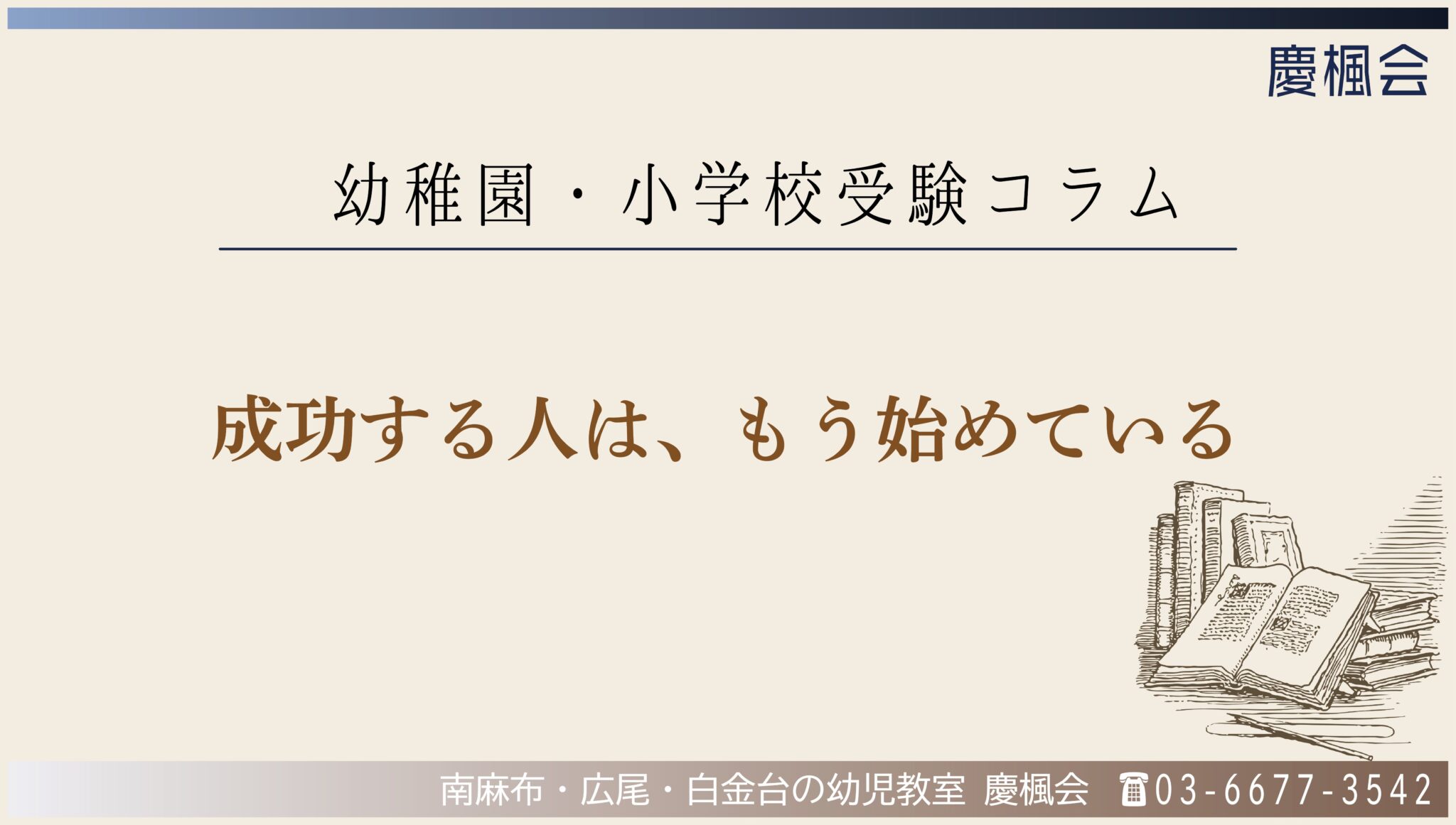
皆さん、こんにちは。慶楓会小学校受験コース主任の松下健太です。
日ごとに空気が澄んで、朝夕の涼しさや虫の声に秋の深まりを感じる季節になりました。
園の運動会も終わり、受験を考える方は、そろそろ来年度のことが気になり始める頃でしょうか。
この時期、「そろそろ受験準備を始めた方がいいかしら」と考える保護者の方が増えてきます。
けれども、その「そろそろ」と思っている間にも、実はもう動き始めているご家庭がたくさんあるのです。
今回は、「成功する人はもう始めている」というテーマで、なぜ早めの計画的な準備が大切なのか、そしてどのように一歩を踏み出せばよいのか、具体的にお話しいたします。
差は、見えないところでついていく
小学校受験における「受験準備」とは、プリント学習を100枚するとか、見栄えのする作品が作れるような工作の練習を始めるとか、そのようなことが本質ではありません。それ以上に大切なのが、家庭の教育姿勢や価値観を明確にし、言語化のした上で生活の中に位置付けていくことです。
長年の指導経験をもとに感じますのは、早い段階から受験を意識して動いているご家庭は、表面的な勉強量以上に、生活の質や会話の深さにおいて、すでに大きな差を生んでいるということです。
たとえば食卓での会話を例に考えてみましょう。「おいしいね」「きれいだね」という何気ない会話の中にも、語彙力や観察力を育てようとする、保護者の教育への姿勢があります。朝の身支度やお手伝い一つをとっても、自分のことは自分でするという習慣を身につけさせるには、それなりに長い時間がかかります。
また、日々の生活の中で、「ありがとう」や「ごめんなさい」といった言葉を自然に用いることができるよう、生活の中で働きかけ、日々の会話の中で自然にやり取りすることができているご家庭は、やはり他の方とはその時点ですでに違います。すなわち、考査で見られる生活力の土台や、他者意識の基盤が、日常の中にもう出来ているのです。
すなわち、一般的にイメージされる「お勉強」ということよりも、むしろ「家庭内の文化のあり方」を整えていくことが、まず第一に大切なのです。
こうした力は、一朝一夕には身につきません。
「いつか、その時が来たら始めよう」と思っている間にも、少しずつ差が広がっていきます。そしてその差は、半年後、1年後には学力の差ではなく、醸し出される空気感の差として表れてきます。
そして、見えない空気感の積み重ねが、やがてお子さんの振る舞いや言葉遣いなど見える形の差となって現れます。
ですから、本格的な試験対策の開始が受験学年になって始まるずっと前から、日常の中において、「成功する人はもう始めている」と言うことができるのです。
「生まれた時」から始めている人々
早い人は、「生まれた時」から準備を始めていると聞くと、「え、そんなに早く?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
けれども実際、私立小学校の教育文化をよく理解しているご家庭では、受験の準備は「受験を意識してから」ではなく、お子さんが生まれたその日から始まっているのです。もっと言えば、お子さんを授かったということがわかったその時から、すでに準備が始まっていると言っても過言ではありません。
これはもちろん、大量のプリントや受験情報を集めるというような、表面的な意味にとどまるものではありません。
お子さんへの語りかけ方、質の良い絵本の選び方、食事や挨拶の習慣、感情の受け止め方、こうした親子の関わりに、いかに意識的になれるか、言うなればその「感性」を、親御様自身が育てているのです。
このように意識的な日常を重ねる中で、自然に教育の土台がつくられていくのです。
家庭内の、ちょっとした場面での親の対応ひとつで、ご両親様で大切にされている価値観が垣間見られることもあります。お子さんが転んだ時に「痛かったね」と共感するのか、「大丈夫、立てるよ」と励ますのか、どちらが正解ということはありませんが、家庭としてどのような価値観を大切にしているかが、その選択に表れると言えます。
こうした積み重ねにより、面接で問われる「ご家庭の教育方針」や「お子様の性格」として評価される、家庭の価値観が形成されていくのです。そのため、準備の早いご家庭ほど、教育の一貫性が自然と生まれていくのです。
一方で、「そうした文化をお手本にできる環境が身近にない」「どのような準備をどのように進めていけばよいか分からない」というご家庭も少なくありません。
だからこそ、後から始めるご家庭ほど、意識的に学び、意図的に家庭内の在り方を見直し、適切な形へと整えようとする努力が必要になります。過去を取り戻してやり直すことはできませんが、未来を見据えて在り方を修正していくことは、今からでも十分可能です。
始めるのが早いほど、意識的に「家庭の文化を育てる時間」に変えていくことが可能となるのです。
後ろ盾がない家庭こそ、早く動く価値がある
私立小学校や名門幼稚園の受験には、独特の文化と背景が伴います。
親が出身であったり、祖父母が関係者であったり、志望校に何かしらの縁があるというご家庭も多く、そうした「文化的後ろ盾」を自然に受け継いでいる場合があります。
しかし、多くのご家庭にとっては、そのような土台はありません。だからこそ、早く動くことに大きな価値があるのです。
たとえば、慶應義塾・東洋英和といった学校では、学力だけでなく、「ご家庭の文化理解」や「宗教観」「礼節」「社会性」といった、受験以前の人格的な基盤が非常に重視されます。これらは、短期間で身につけられるものではありません。受験直前の半年でマナー本を読んだり、直前期に練習を重ねたりしても、にじみ出る品格までは、簡単には整えられないものです。
けれども、だからといって「縁がないから無理」と思う必要はありません。すでに述べたように、むしろ後ろ盾のないご家庭こそ、意識的に、早くから学び始めることに大きな意義があるのです。
本来は、家庭にもとより備わっていて欲しい文化だからこそ、それを有していないという自覚のあるご家庭は、時間をかけて学ぶことが重要です。そのためには、情報を正しく選び、信頼できる指導者から導きを受けて、家庭の中で丁寧に文化を築いていくことが何よりも強い武器になります。
その意味で、早く知ることは、早く備えるということなのです。正しい方向へ舵を切るには、時間が必要です。
そしてじゅうぶんな時間があれば、焦らず、確かな形でお子さんを導いていくこともできるのです。
家庭の軸をつくる準備
受験準備を進めていくうちに、多くのご家庭が気づかれることがあります。
それは、受験とは子どもの対策ではなく、家庭の軸、すなわち価値観や文化を問われるものだということです。
面接や願書でしばしば問われるのは、
「なぜこの学校を志望するのか」
「家庭ではどのような教育をしているのか」
「どのようなお子さんに育てたいのか」
という質問ですが、学校側としては、それらの個別の回答を、バラバラの視点で答えて欲しいわけではありません。
つまり、どの質問であったとしても、本当に尋ねたい本質は共通しているのです。ですから、聞かれ方や質問の切り口がどうあれ、親としての明確な価値観のもとに、それらを表現する言葉をどれだけ持ち合わせているかが問われるのです。
この家庭の軸というものは、言うなれば価値観や文化そのものですから、いざ質問されて、その場で初めて考えてみるという姿勢では、試験官を納得させられるような言葉を紡ぎ出すことはできません。
教育にかける思いは、日々の生活の中で少しずつ形づくられていくものであり、しかも意識して言葉にしていかないと、初対面の他者である面接官をして、納得させるような伝え方をすることはできない、ということです。
だからこそ、早く準備を始めるご家庭ほど、この軸を言語化し、固めていく時間を長く確保することが大事なのです。そのような下地があって初めて、家庭の姿を自然な言葉で表現することができるようになります。
すなわち、受験準備とは、とりあえず有名な塾や教室に通うことで成し遂げられるものではないのです。
まずは家庭の中で「何を大切にして生きているか」という家庭の軸を話し合うこと、それがすべての出発点です。そして軸が定まれば、迷いが減ります。教材を選ぶ基準も、教室を選ぶ基準も、自然と見えてきます。
早く始めるということは、「迷って無駄にする時間を減らす」ということでもあるのです。
今すぐできる第一歩
では、「始める」とは具体的に何をすればよいのでしょうか。ここでは、すぐに取り組みを始めるための視点をいくつかご紹介します。
① 「なぜ受験をするのか」を、ご家庭の言葉で表現する
まずはご夫婦で、あるいはご家族で、「なぜ私立小学校を目指すのか」を率直に話し合ってみてください。「周りが行くから」「良い環境だから」という理由ではなく、わが家が何を求めて、どのような教育に共感するのかを言葉にすることが大切です。この志望の軸があるかどうかで、受験準備の質が大きく変わります。
慶楓会では、見栄や外聞、親のエゴでないかを見つめ直してくださいとお伝えしています。もちろん、それらが全てであってはいけませんが、初めはそんなきっかけで受験を志す人が多いのも実際のところです。しかし、正しい受験準備を重ねた多くの方が、その過程で、幼児期のお子さんを豊かに育むことの尊さを知るようになります。
② お子様と過ごす時間の中で、「考える・話す・待つ」を意識する
受験で問われるのは、知識よりも「思考力」や「社会性」といった、その子の資質や人間性の基盤となる要素です。家庭の中で、「なぜそう思うのかな?」「こんな時は、どうしたらよいと思う?」といった問いかけを重ねることで、お子さんの思考を育てるように心がけましょう。
その際には、急がず待つことも大切です。お子さんが考える時間を尊重し、答えを急がせない親御様の姿勢が、お子さんの粘り強く考える姿勢を育みます。そしてそのように受け止められた感覚が、自己肯定感を養うことにもつながるのです。
③ 教室や学校説明会に足を運んで、「現場」を知る
インターネットの情報だけでは分からないことが、現場にはたくさんあります。先生方の言葉の温度、そこに通う子どもたちの表情、校舎に充ちる空気。それらを体感することで、目指す学校の実像や、教育観が具体的になります。実際に、始めてみないと分からないことが多くあるものです。まず動くことが、最初の学びです。
どんなことでも、初めの動き出しは腰が重いものですが、一度初めてしまえば、その動きを継続していくことをすればよいので、気持ちは楽になるはずです。
動いた人だけが、見える景色がある
「もう少し準備が整ってから」
「子どもがもう少し成長してから」
と考えているうちに、時間はあっという間に過ぎていってしまいます。けれども、始めた方には必ず見えてくる景色があります。
動くことで、迷いは減り、不安だった気持ちは少しずつ解消し、目の前には具体的な課題が見えるようになります。行動するほど、受験が特別な出来事ではなく、日常の延長として感じられるようになります。
最初は恥ずかしそうにしていても、数ヶ月後には堂々と発表できるようになるお子さんの姿や、最初は緊張しながら受けていた面接練習でも、半年後にはご自分の言葉で話せるようになる保護者の姿を、私は何度も見てまいりました。
始めることで、人は変わります。そして変化は、必ず成長へとつながります。完璧な準備をしてから始めるのではなく、始めることで準備が次第に整っていくのです。
勇気を持って一歩を踏み出したご家庭こそが、最終的に「受験を通して最も成長した家庭」となります。
それは合否の結果以上に、お子さんにとってかけがえのない財産となるはずです。
「成功する人はもう始めている」
この言葉の意味は、皆さんを焦らせたいという意図で伝えているのではありません。
そうではなく、「今からでも遅くない。それどころか、今こそが最も早い瞬間である」という希望を胸に、今すぐに未来への一歩を踏みだすための背中を押すメッセージです。
受験準備とは、お子さんを競わせるための活動ではなく、家庭としてどう生きるかを見つめ直す時間です。お子様の成長を信じて、親としてできる最善を尽くす。そうした親としてお子さんに真摯に向き合う姿勢が、お子様にとって何よりの教育となります。
繰り返しますが、動いた方にしか見えない景色があります。
それは、「出口戦略」や「属性論争」のような、幼児の受験を取り巻く情報戦争に翻弄されているうちには決して見出すことができない納得や確信、そして家族としての絆です。
迷っている時間を、学びの時間に変えていく勇気、必要なのは、その最初の一歩を踏み出す意志だけです。
ご家庭の未来を豊かにしてくれる未来への道。
今この瞬間が、その始まりなのです。
執筆
慶楓会 小学校受験コース 主任 松下健太
体験授業・ご面談も随時承ります